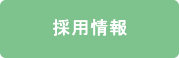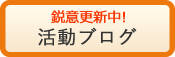春の新生活、ストレスなく元気に過ごそう!
2023/04/17
こんにちは。栄養士チームです。
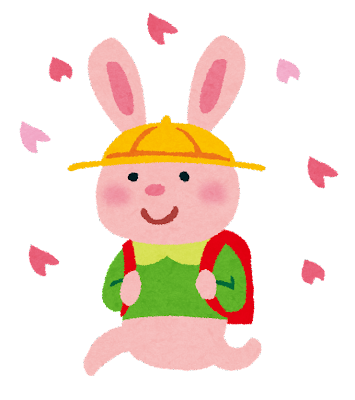
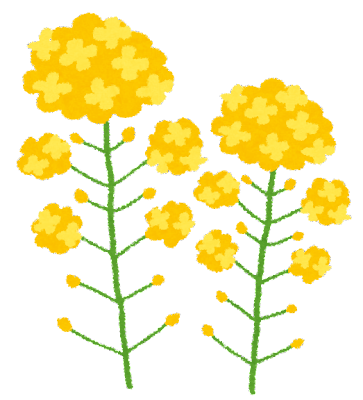
4月といえば、お花見や入学式・入社式などのイベントが多く、心躍る季節でもあります。
その反面、新入生・新入社員などの新生活を始めた方にとっては、新しい環境に慣れず、
不安を感じるかもしれません。
今の時期は昼夜の気温差が大きいため、体調を崩しやすい季節でもあります。
そのため、心身ともに不安定になりやすく、ストレスを感じることも多いでしょう。
そこで今回は、新生活を元気に過ごすためのいくつかのポイントを紹介したいと思います。
【バランスの良い食事でストレス軽減】
私たちの体は、ストレスを感じた時に“特定の栄養素”を消費して、ストレスから身を守ろうとします。
そのため、体内でそれらの栄養素が不足するとストレスに抵抗しづらくなります。
そこで、ストレスの軽減に役立つ栄養素とそれらが含まれる食品について紹介します。
旬の食材は栄養価が高く効率的に栄養素を補うことができるので、
旬の食材を日頃の食事に取り入れてみましょう♪
【その他に気をつけたいこと】
食事や栄養素以外にも、ストレスを軽減するための大切なポイントがあります。
生活リズムを整える
生活のリズムが乱れると、体内時計が狂い、ストレスや不眠の原因となります。
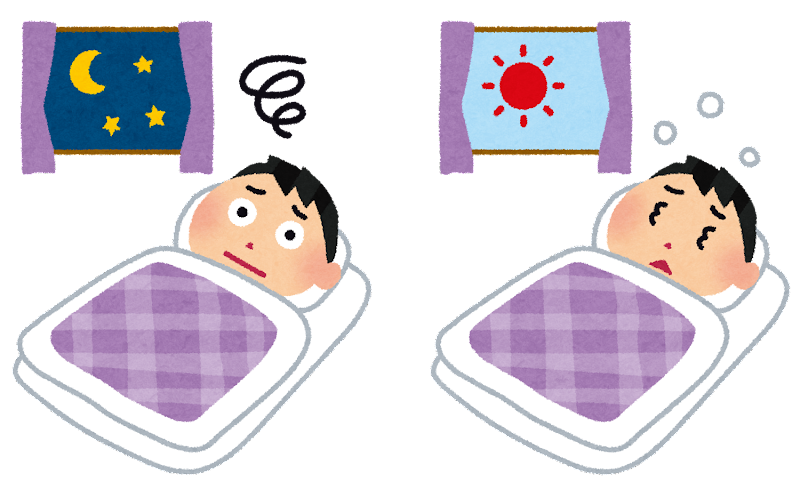
そのため、規則正しい生活習慣を送り、生活リズムを整えることが大切です。
生活リズムを整える上で重要なポイントは、「起きる時間」「寝る時間」「朝昼夕の食事の時間」です。
これらのルーティンが乱れないように続けましょう。
適度な運動をする
体力の維持やストレス解消には適度な運動が効果的です。
ジョギングや散歩、ストレッチングなど、自分に合った方法で運動しましょう。
運動をすることで、ストレスホルモンの分泌を抑え、気分をリフレッシュすることができます。
また、適度な運動は、免疫力を高めて病気になりにくい体を作ることにも関係します。
過度な運動は逆効果になるので、無理のない範囲で行いましょう。

休息をとる
新しい環境に慣れるためにも、無理をせずに休息をとることが大切です。
毎日のスケジュールに、リラックスタイムを組み込みましょう。
お風呂に入ったり、読書をするなど、自分がリラックスできる方法を見つけましょう。
また、休日には十分に休養を取れるようにしましょう。
休日だからといって、様々な予定をビッシリと詰め込んでしまっては、体も心も休まりません。
心と体を休ませるための「自分なりのリラックス法」で休日を過ごしましょう。

睡眠をとる
睡眠不足はストレスや体調不良の原因になるため、しっかりと睡眠をとるようにしましょう。
特に、就寝前にスマートフォンやパソコンを使用するのを避けましょう。
寝る1時間前には画面から離れ、リラックスする時間を作りましょう。

体温調節をしっかりと
寒暖差が大きい時期は、体調を崩しやすくなるだけでなく、ストレスの原因にもなります。
そんな時期の対策として、「薄物の重ね着」をお勧めします。
暑さ・寒さを感じたら、すぐに衣類で調節できるように備えておきましょう。

【おわりに】
新生活を元気に過ごすためには、「バランスの良い食事」「規則正しい生活」「適度な運動」、
そして「適当な休息と睡眠」が不可欠です。ストレスを上手に解消しながら、皆様の心と体が共に健康であり続けられますよう、応援しています。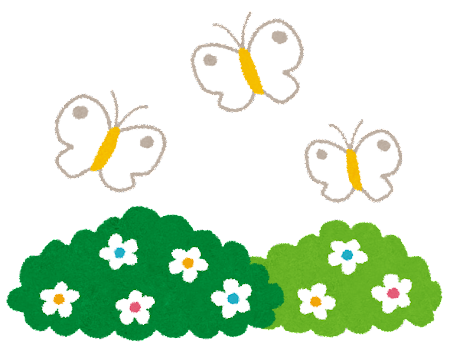
参考
https://www.otsuka.co.jp/college/nutrients/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat510/h25/20130326001/
ストレスと食生活 | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
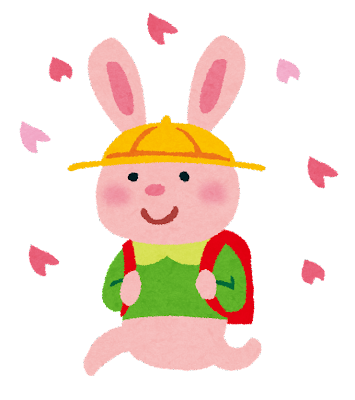
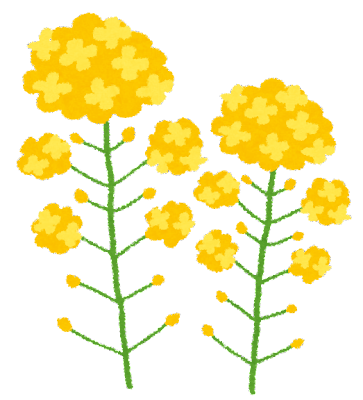
4月といえば、お花見や入学式・入社式などのイベントが多く、心躍る季節でもあります。
その反面、新入生・新入社員などの新生活を始めた方にとっては、新しい環境に慣れず、
不安を感じるかもしれません。
今の時期は昼夜の気温差が大きいため、体調を崩しやすい季節でもあります。
そのため、心身ともに不安定になりやすく、ストレスを感じることも多いでしょう。
そこで今回は、新生活を元気に過ごすためのいくつかのポイントを紹介したいと思います。
【バランスの良い食事でストレス軽減】
私たちの体は、ストレスを感じた時に“特定の栄養素”を消費して、ストレスから身を守ろうとします。
そのため、体内でそれらの栄養素が不足するとストレスに抵抗しづらくなります。
そこで、ストレスの軽減に役立つ栄養素とそれらが含まれる食品について紹介します。

カルシウム:脳や神経の興奮を鎮め、精神を安定させる。牛乳、チーズ、ヨーグルト、大豆食品、小魚、野菜類、海藻類、モロヘイヤなどに豊富に含まれる。
ビタミンB群:抗ストレスホルモンの合成を促し、ストレスを和らげる。精神状態を安定させる。レバー、ハツ、豚肉、かつお、ニンニク、ナッツ類、のり、バナナに多く含まれる。
ビタミンC:抗ストレスホルモンの合成を促し、抵抗力を高める。パプリカ、ピーマン、ブロッコリー、キウイ、オレンジ、いちごなどに多く含まれる。
これらの食品を日常的にバランス良く摂取することで、ストレスに対する抵抗力を高めることができます。ただし、摂取する栄養素が偏っていては、ストレスを緩和することはできません。
日頃から「バランスの良い食事」を心がけてください。
旬の食材は栄養価が高く効率的に栄養素を補うことができるので、
旬の食材を日頃の食事に取り入れてみましょう♪
【その他に気をつけたいこと】
食事や栄養素以外にも、ストレスを軽減するための大切なポイントがあります。
生活リズムを整える
生活のリズムが乱れると、体内時計が狂い、ストレスや不眠の原因となります。
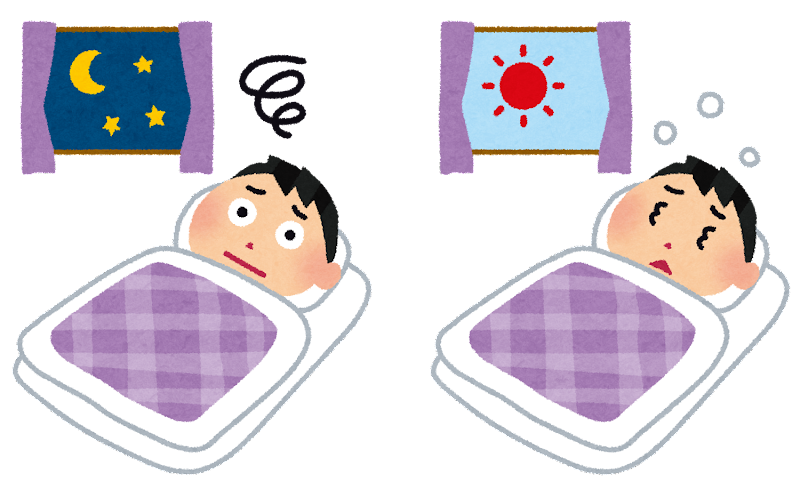
そのため、規則正しい生活習慣を送り、生活リズムを整えることが大切です。
生活リズムを整える上で重要なポイントは、「起きる時間」「寝る時間」「朝昼夕の食事の時間」です。
これらのルーティンが乱れないように続けましょう。
適度な運動をする
体力の維持やストレス解消には適度な運動が効果的です。
ジョギングや散歩、ストレッチングなど、自分に合った方法で運動しましょう。
運動をすることで、ストレスホルモンの分泌を抑え、気分をリフレッシュすることができます。
また、適度な運動は、免疫力を高めて病気になりにくい体を作ることにも関係します。
過度な運動は逆効果になるので、無理のない範囲で行いましょう。

休息をとる
新しい環境に慣れるためにも、無理をせずに休息をとることが大切です。
毎日のスケジュールに、リラックスタイムを組み込みましょう。
お風呂に入ったり、読書をするなど、自分がリラックスできる方法を見つけましょう。
また、休日には十分に休養を取れるようにしましょう。
休日だからといって、様々な予定をビッシリと詰め込んでしまっては、体も心も休まりません。
心と体を休ませるための「自分なりのリラックス法」で休日を過ごしましょう。

睡眠をとる
睡眠不足はストレスや体調不良の原因になるため、しっかりと睡眠をとるようにしましょう。
特に、就寝前にスマートフォンやパソコンを使用するのを避けましょう。
寝る1時間前には画面から離れ、リラックスする時間を作りましょう。

体温調節をしっかりと
寒暖差が大きい時期は、体調を崩しやすくなるだけでなく、ストレスの原因にもなります。
そんな時期の対策として、「薄物の重ね着」をお勧めします。
暑さ・寒さを感じたら、すぐに衣類で調節できるように備えておきましょう。

【おわりに】
新生活を元気に過ごすためには、「バランスの良い食事」「規則正しい生活」「適度な運動」、
そして「適当な休息と睡眠」が不可欠です。ストレスを上手に解消しながら、皆様の心と体が共に健康であり続けられますよう、応援しています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
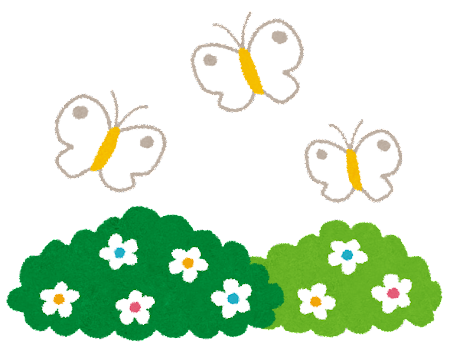
参考
https://www.otsuka.co.jp/college/nutrients/
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat510/h25/20130326001/
ストレスと食生活 | e-ヘルスネット(厚生労働省) (mhlw.go.jp)
アーカイブ
- 2024年10月(2)
- 2024年9月(1)
- 2024年8月(1)
- 2024年7月(2)
- 2024年6月(1)
- 2023年8月(1)
- 2023年7月(1)
- 2023年6月(2)
- 2023年5月(4)
- 2023年4月(1)
- 2023年3月(1)
- 2023年2月(1)
- 2023年1月(1)
- 2022年12月(1)
- 2022年11月(1)
- 2022年10月(2)
- 2022年9月(2)
- 2022年8月(2)
- 2022年7月(4)
- 2022年6月(5)
- 2022年4月(5)
- 2022年3月(3)
- 2022年2月(3)
- 2022年1月(1)
- 2021年12月(5)
- 2021年11月(5)
- 2021年10月(2)
- 2021年9月(3)
- 2021年8月(5)
- 2021年7月(3)
- 2021年6月(2)
- 2021年5月(1)
- 2021年4月(5)
- 2021年2月(1)
- 2021年1月(3)
- 2020年11月(5)
- 2020年10月(5)
- 2020年7月(3)
- 2020年6月(2)
- 2020年5月(1)
- 2020年4月(2)
- 2020年3月(2)
- 2020年2月(3)
- 2020年1月(3)
- 2019年12月(1)
- 2019年11月(5)
- 2019年10月(4)
- 2019年9月(1)
- 2019年8月(2)
- 2019年7月(2)
- 2019年6月(1)
- 2019年5月(1)